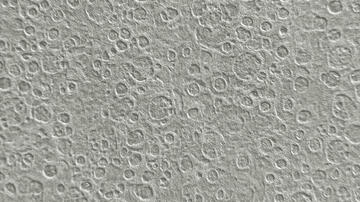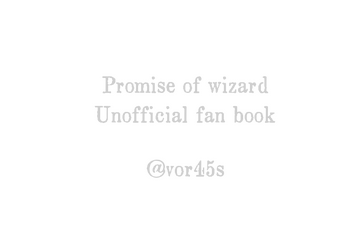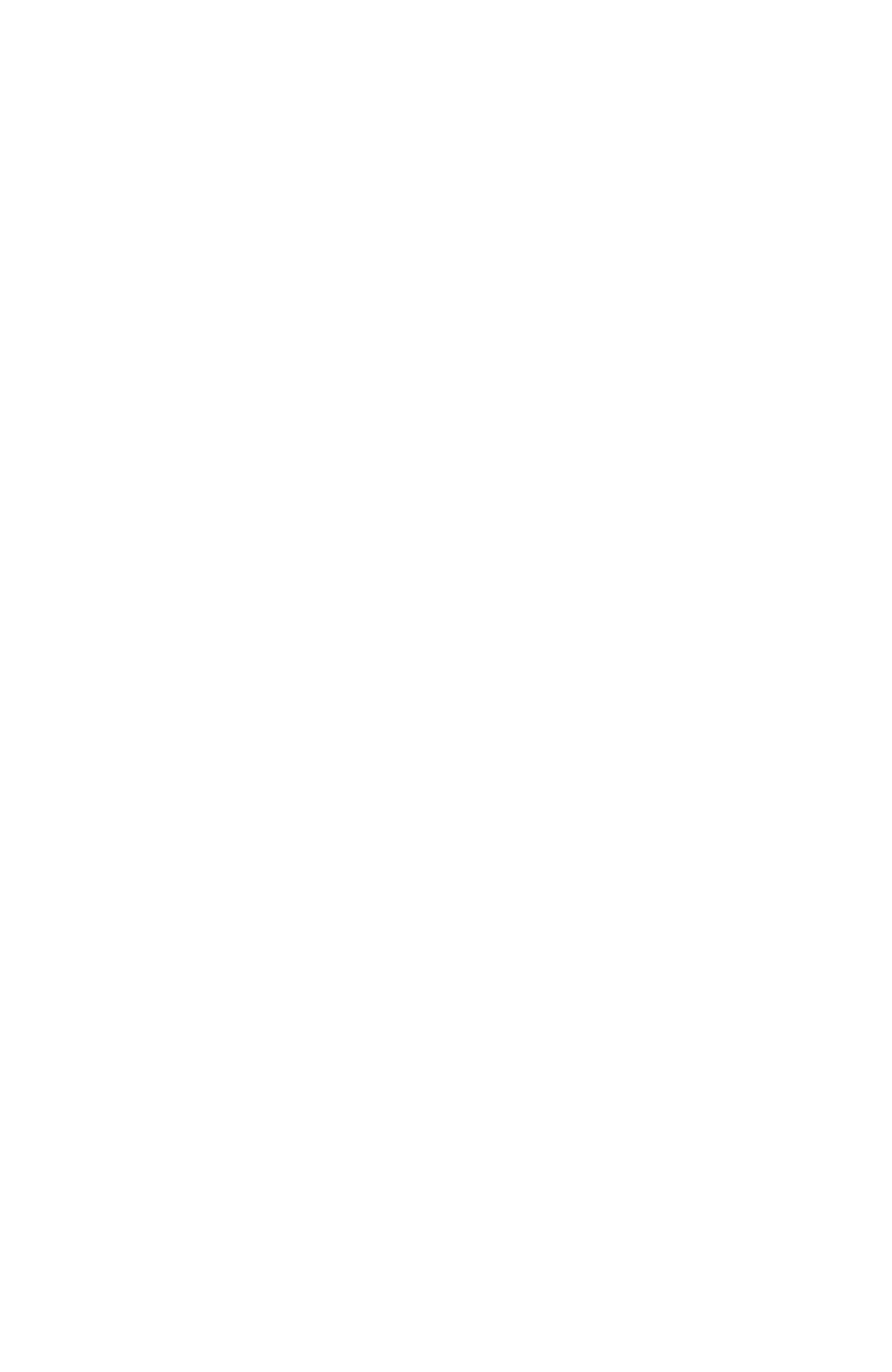
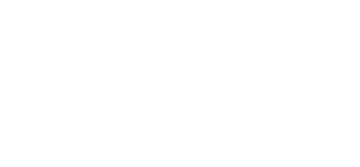

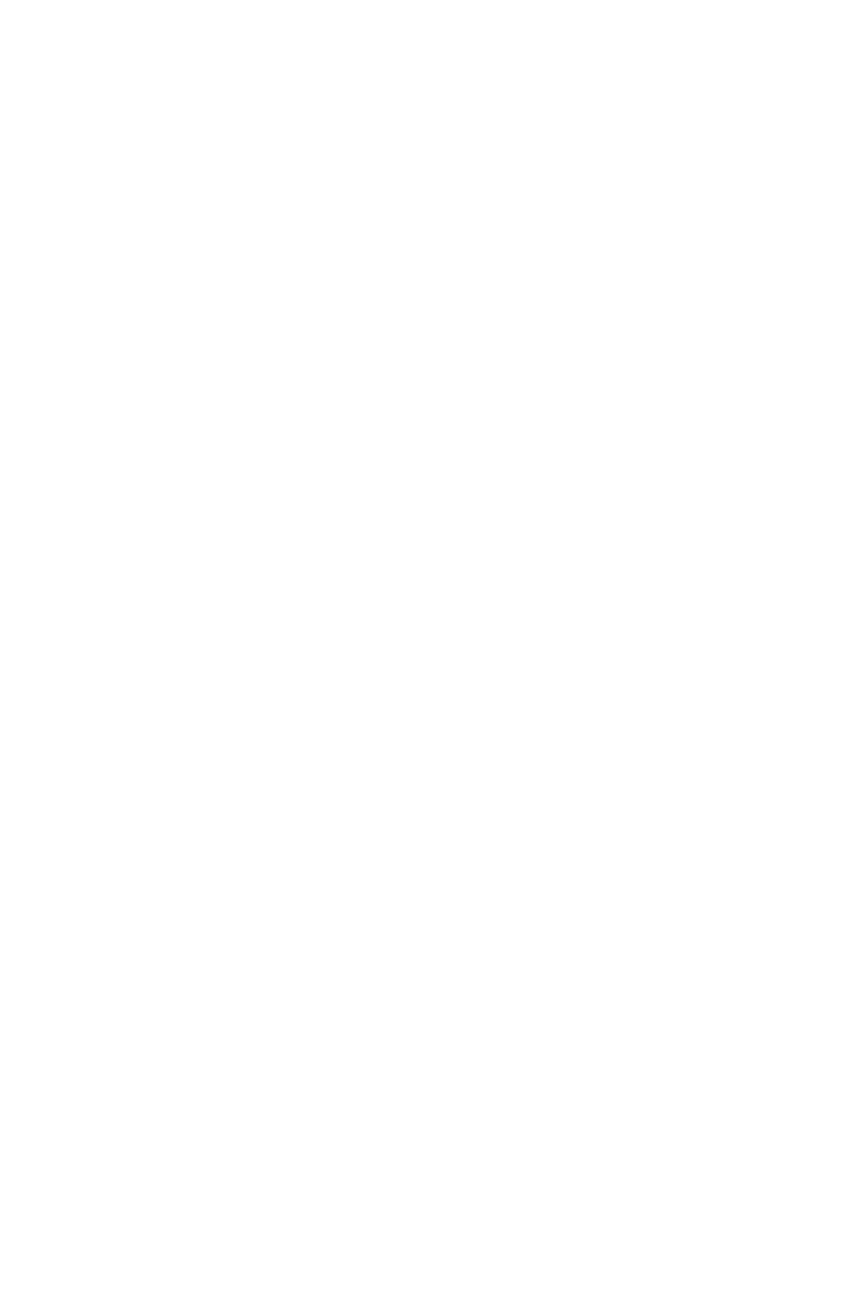
初夏の眩しい風が渡る。
額を寄せて窓辺に腰掛ける。
ここで昼中の星々を探すのが好きだった。
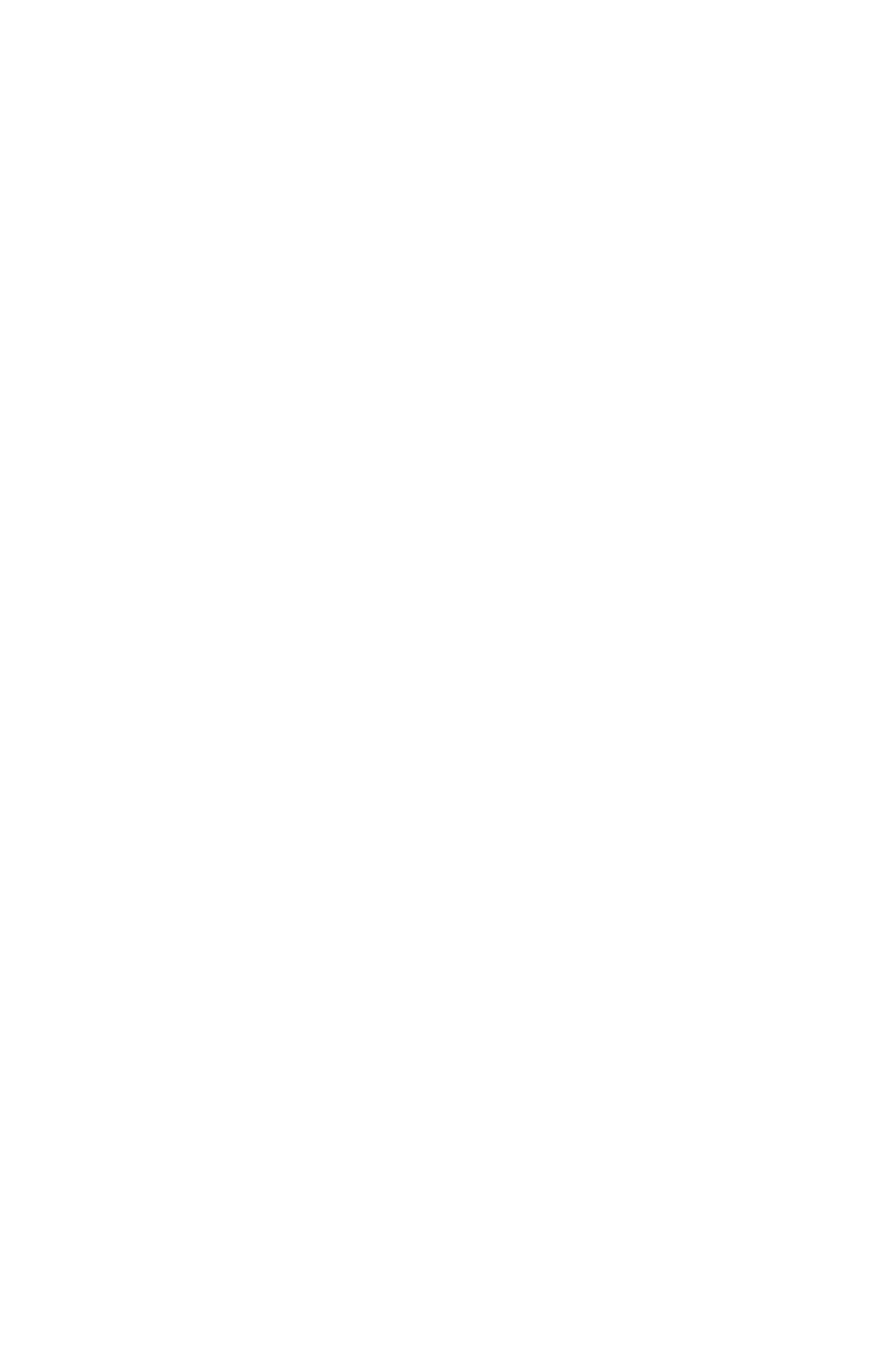
波打ち際まで近づいて、打ち寄せる影を追った。
海はこの夜の色だ。
そうして目線を上げた先の水平線上に、天の河は溶け出していた。
愛しいものを夏の日に喩えるのだと、とある賢者は言った。
あれは確か満月の晩だった。
何千回と過ごした夏の日についてこの頃考え巡らせていたが、
喩えるならだから、きっとこんな夜のことと思いたい。
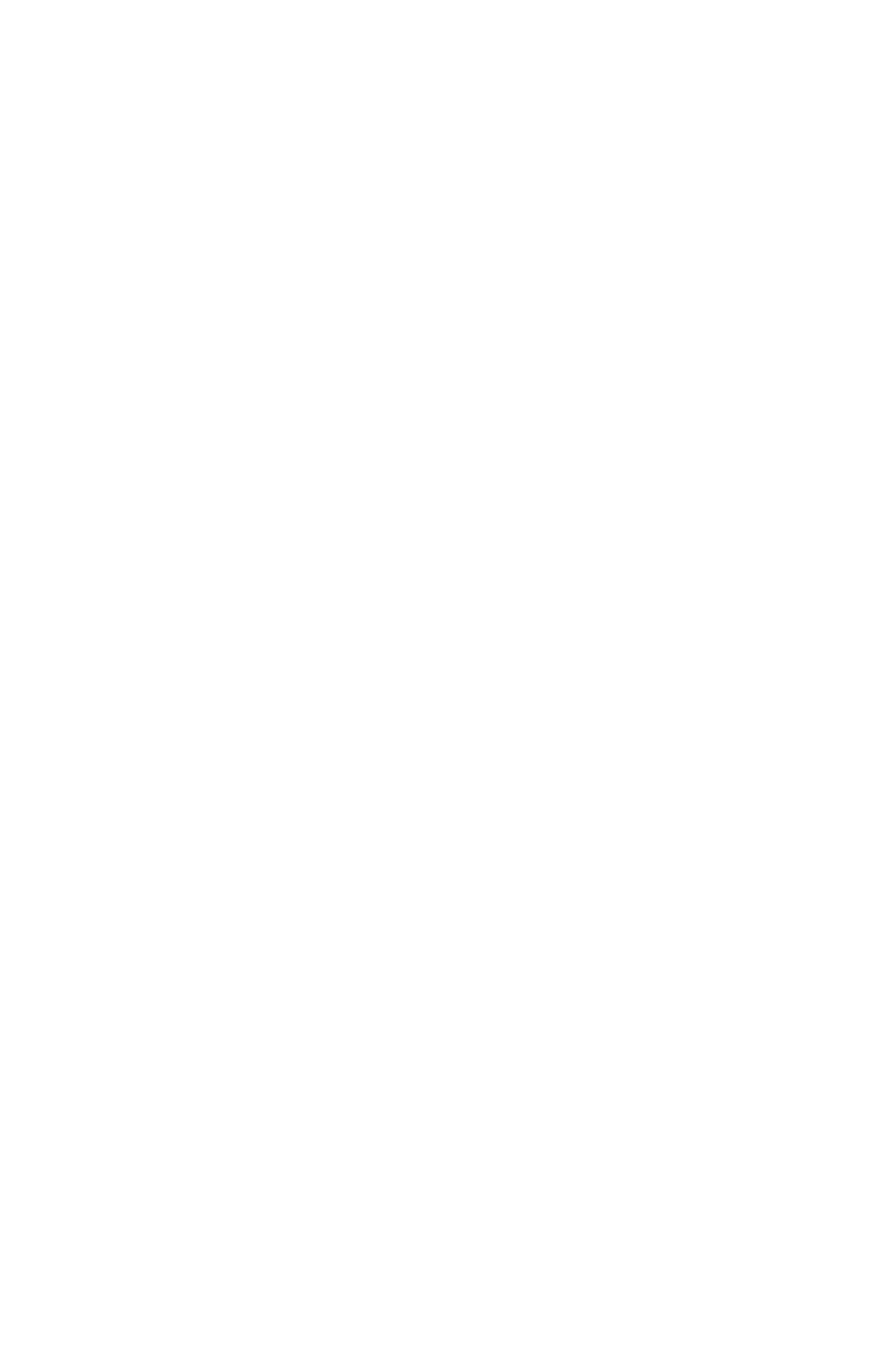
月光の道を長い散歩に出ていた。
今日は天文台に来客があるのだが彼はきっと夜更けにしかやってこない。
秋は露が下りるものだが、
それは何も地上に限ったことではないようだ。
空も存分に水を吸って軟らかく、深くなる。
「彗星現る、最接近は月末か」今回のものはまだ幼い頃に一度見たきりのあの彗星だった。
初めて厄災を見上げた時のあの透き徹る気持ちを殊更に憶えている。
踏み出した芝が夜露に濡れていて、つま先が冷たかったことも。
それが綺麗な満月だったことも。
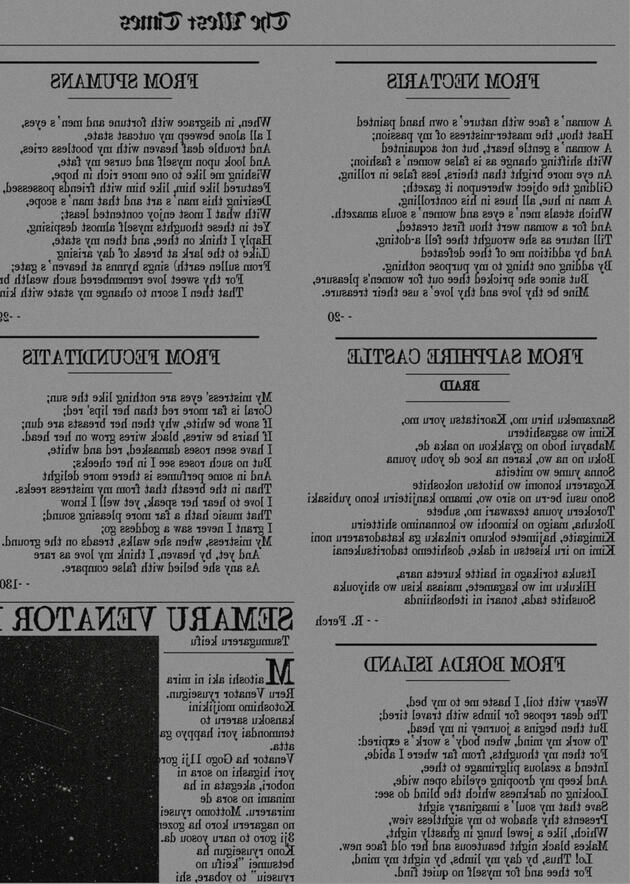

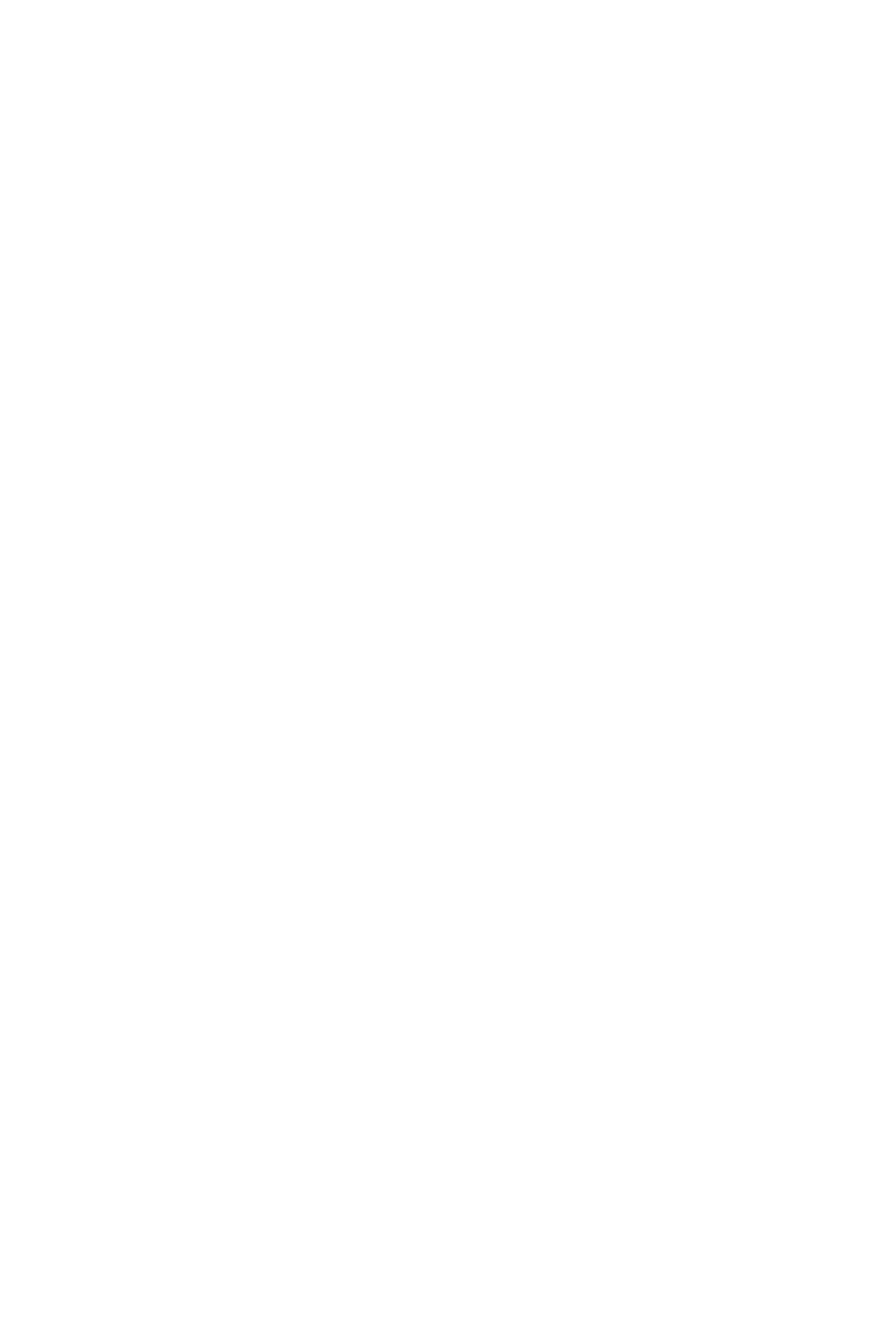
この招待状は流星群の降る頃に送られたものだ。
天文台と共にスコーピオンの心臓が燃えていたのを
今も鮮明に覚えていた。
深くふかく息を吸う。凍えた大気が喉を刺す。
そうして、